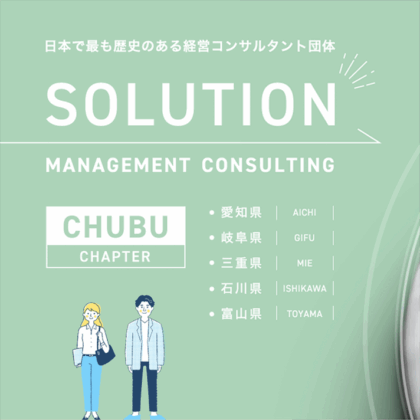プロパガンダの本質とマーケティングの原点
2025/3/18配信

「実践経営講座 No.56」
マーケティングの原点と本質がテーマです。
プロパガンダの本質とマーケティングの原点
◆ プロパガンダの起源
2024年アメリカ大統領では、プリントメディア、放送、SNSを駆使した、プロパガンダ的なプロモーションの賛否が議論を呼びました。
プロモーションは、マーケティング4P(製品・価格・流通・プロモーション)の一つです。
プロモーションの中核となる広告宣伝の起源は、1450年頃、ヨハネス・グーテンベルクの活版印刷術の発明と言われています。
活版印刷により、ローマキリスト教会の免罪符(贖宥符)が大量に印刷、販売され、拝金的な教会の世俗化が進みました。
これに対し、マルティン・ルターは聖書中心主義を掲げ、1517年「九十五箇条の論題」を著して印刷配布、教会の世俗化を激しく批判し、宗教改革を唱えます。
ルターの主張は瞬くまにヨーロッパに伝播し、ローマキリスト教会は、カトリック教会(旧教)とプロテスタント教会(新教)に分裂、後のヨーロッパを二分する三十年戦争につながります。
三十年戦争では、互いに敵対する王侯を悪魔の化身としてポスターに印刷し、敵が絶対悪であると信じ込ませる、広告宣伝が展開されます。
この宗教改革と三十年戦争の広告宣伝が、今に至るプロパガンダの始まりであり、プロモーションの原点であったかもしれません。
プロパガンダ(Propagare)は、「福音」を広める「布教」「宣教」「伝道」という意味のラテン語でしたが、グーテンベルクの活版印刷術が、現在のプロパガンダとプロモーションの原形を生み出したと言えそうです。
ちなみに活版印刷術は、火薬、羅針盤とならびルネッサンスの三大発明とされています。
◆ 「我が闘争」とプロパガンダ
アドルフ・ヒトラーは、「我が闘争」(1925年刊)の中で、プロパガンダの本質を以下の様に語っています。
「大衆のほとんどは、自分の意見というものを持たない」
「大衆は学者でもなければ外交官でもない、抽象的な道理は理解できず、感情の世界に生きようとする」
「大衆の大半は、冷静な分別より感情によって動く。大衆は向背の態度を感情で定める」
「大衆の感情は単純である。肯定か否定、愛するか憎む、善か悪か、真か偽かであり、一部はそうだが、一部はこうだなどと細かに考えることはない」
「大衆の心を獲らんとするには、大衆の心の鍵を掴まねばならない」
「敵を捉え、これを味方にするのが宣伝である」
「広告は大衆を目安とし、肝心な要点だけを掲げる」
「宣伝の文章は曖昧な字句を使わず、一点の疑いも入れぬ形式とする」
「宣伝は、いろいろな権利を較量するのではなく、主張すべき権利だけを主張する」
「宣伝は常に自分の方の利益になる事実だけを伝えればよい」
大衆は意見を持たない、主張を端的に短い言葉で、感情に訴えれば意のままに動かせる。
ヒトラーは、第1次世界大戦従軍中、敵である連合国側のプロパガン手法と大衆心理を、このように冷徹に分析していたのです。
そして、その後にナチス政権が樹立され、第2次世界大戦に突き進むことになります。
◆ プロパガンダ的プロモーション
一般的にヒトラーは、ユダヤ人や共産主義者を虐殺した、冷酷非情な独裁者とされています。
しかし、ナチス政権は、1933年ワイマール憲法のもと選挙で選ばれた政権であり、反ユダヤ主義、反共産主義を支持したのが、国民であることも事実です。
意見を持たず、主張を鵜吞みにする大衆心理につけ込む、プロパガンダ的な選挙プロモーションは、アメリカ大統領選をはじめ、90年経った今も変わりません。
政治活動に限らず、マーケティングも同じです。
商品に対し、価値観や選択基準を持たない消費者がいるから、マーケティングが効くのであり、プロパガンダ的な販促プロモーションも有効となるのです。
SNSでの短いコピーや動画、端的な表現に慣らされ、人工知能に頼って、考える習慣を失くしつつあるのが現代です。
プリントメディアしかなかった時代に比べ、プロパガンダの手法もハイブリット化しています。
プロパガンダと思わせず、消費者の意識と行動を操ることが、マーケッターの役割の一つです。
ただしプロパガンダ的プロモーションには、リテラシーとモラルが伴うことも忘れてはなりません。
「我が闘争」は、独裁者、虐殺者の禁断の書とされています。
一方、プロパガンダと大衆心理を読み解くテキストとして、密かに読み継がれてもいます。
組織の統率やマーケティングの根底に隠された、プロパガンダの本質を知ることは、経営者やコンサルタントにとっても有益なことです。
編集後記
「我が闘争」は、人種差別を根底に民族浄化を招いた禁忌の書として、世界中でタブー視されています。
しかし、民族浄化は、中国のウイグル、チベットの例だけでなく未だに続いています。
幸福度ランキング上位のデンマークですら、1969年までグリーンランドのイヌイットに対し、強制避妊やデンマーク語、文化の強要による、民族浄化を行っていました。
民族浄化は、とうてい一人の人間だけで成しうるものではなく、多くの人間の同意があって成立するものです。
未だ解決されない、人類普遍の問題の一つが民族浄化なのです。
企業経営においては、プロパガンダの本質を正しくマーケティングやイノベーションに活かし、社会に役立つ普遍的な企業価値の創造に努めたいものです。
(文責:経営士 江口敬一)