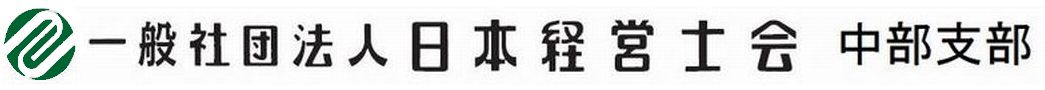「沈黙の春」から環境と経営を考える
2023/10/3配信
「実践経営講座 No.36」
環境と経営の関係を、歴史を紐解きながら考察する話です。
「沈黙の春」から環境と経営を考える
◆ 環境と経営を考える
「環境経営」なる言葉を筆者が初めて耳にしたのは、2010年頃。
この言葉の不可解さはともかく、環境と経営について、歴史と自身の体験を紐解きながら、考察したいと思います。
筆者の地元名古屋市では、1999年、環境団体や野鳥の会などの反対運動により、渡り鳥の中継地である藤前干潟での、最終ごみ処分場建設計画が、突如撤回されました。
ごみの行き場を失った名古屋市は、「ごみ非常事態」を宣言、市民のごみ減量への関心がにわかに高まりました。
巷にはエコやリサイクルの言葉が溢れ、企業も市民団体や行政から、事業ごみの減量対策と排出者責任を強く問われる事態に陥ります。
当時、環境情報紙の発行人であった筆者も、市民、行政、事業者からなる「なごや古紙リサイクル協議会」、業界団体による「名古屋リサイクル推進協議会」の事務局長として、ごみ減量と古紙のリサイクルに関わることに。
特に古紙リサイクルの基幹を支える回収業者が、古紙の需給や相場価格の影響を受けず、安定的に古紙回収を継続できるよう、制度化による古紙回収システム作りに、行政担当者と共に腐心したことを、今でも覚えています。
2005年愛知万博(愛・地球博)でも、万博会場予定地でオオタカの営巣地が見つかるや環境保全を訴え反対運動が起こり、会場予定地を一部変更のうえ博覧会テーマも急遽、「自然の叡智」に。
この万博でも公式ホームページの記事編集と博覧会情報紙の制作を担当、広報関連で運営に携らさせていただきました。
ごみ処理場も博覧会開催も、新たな事業を行おうとすれば、環境に関わる問題と課題が顕在化し、エコとエゴが交錯して軋轢を生むことも体験しました。
また、当事者の一人として環境問題、課題に向き合った経験は、環境とは何かを考察する機会も与えてくれました。
◆ 環境と経営の普遍的論議
環境と経済、経営を論じるには、「知の爆発」の時代にまで、遡る必要がありそうです。
約2500年前、エコロジーとエコノミーの語源となる言葉がギリシャで生まれました。
同じ頃中国では、諸子百家の一つ道家が、文明と経済の発展による物質的欲求には限界があり、人為的な開発は止め、自然の一部として質素に暮らすことが、人間の幸せであると説いていました。
一方で儒家は、王侯貴族は豪奢な邸宅に住み、華美な衣服と宝飾品を身に付け、庶民との身分格差を示してこそ、封建的な秩序と文明の発展は維持されると主張。自然は、人間の開発の対象との考え方であったようです。
人間も自然の「環」の一部とする道家。人間は、自然の「環」の外にあるとする儒家。
人間も生態系の一部なのか、生態系は人間を必要としていないのか。
人間は自然の「環」の「境」の内にいるのか、外にいるのか。
環境に関する議論は、すでに、この時代から現代に続く、普遍的なものと言えそうです。
◆ 「沈黙の春」と「複合汚染」
「自然は沈黙した。うす気味悪い。鳥たちは、どこへ行ってしまったのか。みんな不思議に思い、不吉な予感におびえた。… 『沈黙の春』の訪れであった。」
1962年に出版された、発生遺伝学・海洋生物学者であったレイチェル・ルイーズ・カーソンの著作、「沈黙の春」(原題「Silent Spring」)冒頭の一部です。
「沈黙の春」は、農薬などに使われるDDTなど化学物質が自然環境と、生体濃縮を通し人体に及ぼす影響について、科学的根拠を示し、その危険性とコントロールの必要性を警告した著作で、環境問題と企業活動を語るうえでの原典とされる書です。
「沈黙の春」出版の衝撃は大きく、市民の厳しい追及に化学薬品企業は、連日、新聞、雑誌に、農薬を失くせば農作物は害虫に食い荒らされ、食糧難に陥るとの反論広告を載せ、議会にもロビー活動を行い、レイチェル排斥への世論誘導を強め続けました。
翌1963年、ジョン・F・ケネディ大統領は、特別科学委員会に農薬に関する調査と報告書の提出を命じます。
報告書でも、農薬に含まれる化学物質の人体や自然環境への影響が指摘され、結果的にレイチェルの主張が認められることに。
この報告書を機に、化学物質を規制する動きは欧米全体に広がり、自動車の排気ガスを規制するマスキー法などにも繋がっていきます。
世論に左右されず、科学性と社会性を優先し、異端の言であっても聞き入れるケネディの判断は、トップリーダーの在るべき姿として評価されるべきものです。
ケネディは化学薬品企業のみならず、既得権を持つ大企業、組合に対しても同様な姿勢で臨み、農薬に関する調査を命じた同年1963年11月に暗殺されます。
暗殺理由の真偽は不明ですが、国家経営において、ステークホルダーの既得権を排除し、革新をもたらすのは、命懸けだったのかもしれません。
企業経営においても、本気で経営革新を目指すのであれば、満身創痍の覚悟が社長には必要です。
レイチェルもケネディ暗殺の翌1964年4月に病没するも、現代の環境保護活動の原点の人物として高く評価されています。
日本の現代の経営と環境を知る上で欠かせないのが、1975年に出版された日本版「沈黙の春」とも称される、有吉佐和子の「複合汚染」です。
日本の農薬や化学肥料、界面活性剤が生態系と人体に与える影響や水俣病、四日市ぜんそくなど公害病の実情と背景を丹念に取材したノンフィクション小説。
特筆すべきは、当時すでに生体濃縮に危機を抱いた農家の有機農法など、問題提起だけでなく、課題解決策の事例も合わせて紹介していることです。
また、マスキー法に適合したホンダのCVCCエンジンについて、本田宗一郎氏に直接説明を聞いたものの、専門的で理解できず、取材帰りのタクシー運転手の簡略な解説で、すんなり納得できたくだり。
他にも、やたらアカデミックに語り威厳を装う学者の話に辟易する場面など、解決事例を示し簡潔に説明する必要性など、経営コンサルタントにも、参考になりそうな場面も多く記載されています。
経営分析では、現状に至る過去からの経緯を把握するのは、必須です。
「沈黙の春」と「複合汚染」は、環境コンサルタント、環境経営士と称する方々には、現代の環境と経営を語る上での教養として、一度は、お読みいただければと思います。
◆ 「環」と「境」
そもそも人間が他の生物と違うのは、自然に適応するだけでなく、自然を人工物に変えて、自ら環境を整える力を生きるすべとして、持ち合わせていることです。
但し、自然を搾取し、変え過ぎると自らの生存も脅かされかねない。
だから、自然の「環」が途切れぬよう「境」を繕い続け生を保つ。
人類の営為の観点から見れば、生きるため自然を人工物に変えことが事業であり、事業を継続しながら自然の「環」と「境」を保つのが、経営とも考えられます。
「環境経営」をあえて定義すれば、単に自社の事業だけでなく、地球規模でのサプライ・バリューチェーンを含めた中で、「環」と「境」を維持することに配慮した、企業活動とでも言えるでしょうか。
GXやインターネットの超高速化は、莫大な市場を開拓した半面、世界的に膨大な電力消費を招き、見えざるところで「境」を越え「環」を壊している可能性も。
環境の概念をもたらした、「沈黙の春」から60年以上を経た今、時代はそろそろ、新たな知見を求め始めているのかもしれません。
編集後記
先日、環境経営のコンサルタントと称する方から、世界の環境活動の主流はSDGsであるとの話を伺いました。
しかし、私は海外でSDGsのパレットマークを一度も目にしたことがありません。
曖昧な目標を掲げ、グリーンウオッシュの疑いを招く恐れからか、そもそも日本だけの取り組みなのかは不明です。
時間軸だけでなく、世界に目を広げる水平軸の視点も、コンサルタントには必要だと思います。
(文責:経営士 江口敬一)