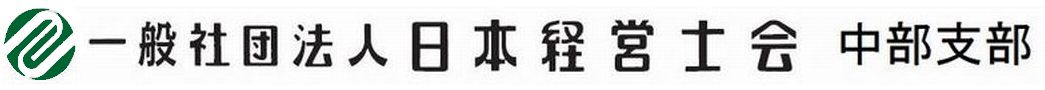ある視点2 王陽明 知行合一と言行不一致
2024/6/18配信
「実践経営講座 No.47」
陽明学の経営への活かし方がテーマです。
ある視点2 王陽明 知行合一と言行不一致
◆ 朱子学と陽明学
「知行合一」、企業の社訓や行動規範に、よく掲げられている言葉です。
知(学び)は、行いと一体である、との意味ですが、経営の場面では、会社の意思である理念や目標に対し、行為や行動を一致させる、との意図で使われるようです。
知行合一は、「心即理」、「良知」、「無善無悪」など、「陽明学」の核心をなす定理の一つです。
陽明学は、中国明代中期に、王陽明(王守仁)により創始された儒学の一派で、「朱子学」と対照をなす学派です。
朱子学は、人の心を性(仁、義、礼、知、信)と情(感情、欲望)に分ける、性即理を命題とし、人は生まれながら善であり、情を捨て、性(五常)を拠り所に人と社会を正す、との考え方。
これに対し、陽明学は、人の心は性も情も一体であるとする、心即理を命題とし、この世に善人も悪人もいない(無善無悪)、人には生まれながら何が善で、何が悪かを知る力(良知)がある、だから善を知り、行いと一体化(知行合一)すれば、人と社会は正せる、との考え方。
良知を発揮する工夫の実践が、陽明学の根本的な教義です。
王陽明は、朱子学を、実践を怠り、堕落した出世のための空論である、と切り捨て、朱子学に基づく政策も、痛烈に批判したと言われています。
その心情は、評論家から論語のご高説を聞かされ、きれい事だけで経営ができるのか、と反発したくなる社長の心情に重なりそうです。

◆ 陽明学の創始
それもそのはずで、王陽明は、皇帝に仕える官僚として、反乱軍の討伐や制度の策定などで活躍した、軍略家、政治家であり、ただの儒学者ではなかったからです。
この頃の明は、地方での農民の反乱や、流民となった流賊の暴動が相次いでいました。
王陽明は、度々、軍を率いて反乱を鎮圧し、軍政を敷いて、地方の治安を回復するなどの活躍を見せています。
一方で、宦官の専横政治を批判し、辺境に左遷されたこともあり、その時期(1508年)に、陽明学は、創始されました。
陽明学は、反乱鎮圧と軍政、政争の生々しい現実を、当事者として目の当たりにした、王陽明の人間観察から、生まれたものなのです。
現実に向き合う機会もない学者が唱える、従来の儒学に、王陽明が苛烈に疑問を呈したのも、当然のことかと思われます。
学者は、軍を指揮することも、政務を司ることもないのですから。
◆ 大局の良知と知行合一
1517年、帝位を狙った「寧王の乱」で、王陽明は、勅命を待たず兵を集め、孫子の如く敵の虚を突き、火計を操って10万の敵兵を壊滅させ、首領らを捕らえています。
「君臣の義」を重んじる儒教では、臣下が勝手に徴兵し兵を動かすなど、ありえないことです。
軍政では、地方の郷村に「十家牌法(じゅっかはいほう)」の制度を施行し、相次ぐ農民反乱を鎮めています。
十家牌法は、10軒単位で隣組を組織し、相互監視のため、家ごとに戸籍、性別、年齢、職業、容貌を記した札を作り、村内の移動や流民の流入をチェックし、違反があれば連帯責任を負わせる制度で、性悪説に立つ法家の韓非子さながらです。
これも、性善説に拠る従前の儒教では考えられず、陽明学の無善無悪にすら背き、言行不一致にも問われそうです。
それでも結果は、謀反による混乱を事前に阻止し、地方の秩序を回復するなど、大きな成果を社会にもたらしています。
彼にとって、君臣の義も、自らの無善無悪も、現実に役立たない時は、小善に過ぎず、独断の徴兵も十家牌法も、「大局の良知」を求めた知行合一であり、当然の帰結だったのかもしれません。
現実の内外の状況に向き合い、局面全体を何が善で、何が悪なのかを見極め、大局の良知を実践することは、現代の経営者にも、求められるものです。
社員には社員の、社長には社長の、それぞれの良知を合し、発揮することで、企業の成長と社会貢献に繋げることが、陽明学の経営への活かし方の一つだと思います。
編集後記
軍事、行政に卓越した実績を残した王陽明は、思索の人であり、反面、激情の人であったと言われています。
その激情こそが、知と行の合一を説く、彼の根源だったのかもしれません。
最期も、反乱討伐後、病により「帰心矢の如し」の感情にかられ、勅命を待たず帰郷の途につき、船中で没しています。
人の心は、到底、性と情では分けられない心即理であることを、自身の生涯をもって語っているのも、王陽明、その人の魅力の一つです。
(文責:経営士 江口敬一)